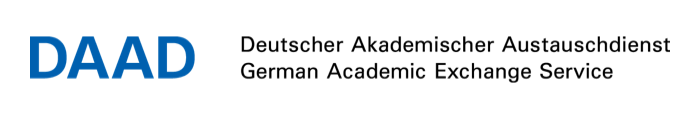第1回 Kamogawa Talk 「日独交流の間(あいだ)からSDGsを考える」
テーマ: 「ボーダーに挑むものたちーグローバル時代における「移民」の再考」
日 時: 2019年12月20日 15:30-17:15
場 所: ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川ホール(第1部)、Café Müller (ネットワーキング)
パネリスト: Dr. Andrey Damaledo(東南アジア地域研究研究所Post-Doctoral Fellow)(略歴)
Dr. Rumen Petrov (Sociologist, New Bulgarian University)(略歴)
プログラム・講師紹介: 当日配布資料はこちら
第1回 Kamogawa Talkの概要
ゲーテ・インスティトゥート 大阪・京都と京都大学学術研究支援室(KURA) が共同で実施する、若者世代の日独交流を促進し、SDGs達成を視野に知見を交換する討論会・交流会です。
京都の地における学術と文化環境は、明治以降、ドイツとの密接な交流の中で育まれてきました。近年になっても学術的な連携や学生の留学先として交流が盛んですが、人々をとりまく文化や環境が地球規模で大きな変化を迎え、日独交流に対する関心・期待は多様化つつあります。
国内、あるいは二国間の双方向だけで問題を議論することは、もはや適切とは言えず、また、それだけでは問題解決につながりません。重要なのは、多国間の、あるいは多角的な議論です。これは文化活動にも、学術研究にも当てはまります。文化と学術、いずれの分野でも、成果を挙げるためには、隣接する分野、あるいは隣国の考え方や発想を取り入れていくことが大切です。
京都大学は、国連の持続的な開発目標(SDGs)への貢献という旗を掲げ国際交流を推進していますが、先進的な政策を牽引するドイツは、SDGsの達成においても注目されています。ゲーテ・インスティトゥートも、その指針として、「市民社会との連携」を新たな目標に掲げています。とくに若手世代が日独の文化交流を通じて知見とネットワークを広げ、SDGs達成にむけて国際的な社会で活躍することが未来の日独交流を形作ることにつながります。
第1回目は「移民」をテーマに、京都大学-DAADパートナーシッププログラムの採択研究者がドイツとの共同研究を通じて得た発見をもとに紹介し、広く一般の参加者を交え、文化と学術を超えた視点でディスカッションを行います。トークの後は、館内のドイツカフェ『カフェ・ミュラー』にて、ドイツビールを片手に交流をお楽しみください。
*本プログラムや海外研究留学に関心をお持ちの方、とりわけ若手研究者(大学院生、ポスドク研究員等)にとって、過去の採択者・留学経験者や日独関係機関・財団等の担当者と情報交換を行うことができる良い機会ですので、ぜひお誘い合わせの上お集りください。
[プログラム・申し込み]
・日 時: 12月20日(金)
・第1部 15:30-17:15 「ボーダーに挑むものたちーグローバル時代における「移民」の再考」
「国家」、「民族」、「文化」ー 人はどのようにしてどのような境界線を超えたり引いたりするのか。「アイデンティティー」をめぐる世論が勢いを増やしつつある今、学術の最前線で活躍している研究者2人とともに、文化人類学、政治学、社会心理学、様々な観点から我々を取り巻く、もしくは締め出す「ボーダー」を問い直し、そして皆様との「ボーダーレス・ディスカッション」を通して新たな「移民論」の可能性を手探りしてみませんか?
パネリスト Dr. Andrey Damaledo(東南アジア地域研究研究所Post-Doctoral Fellow)(略歴)
Dr. Rumen Petrov (Sociologist, New Bulgarian University)(略歴)

東ティモールの首都ディリの風景 ©︎atosan, iStock / Getty Images Plus, Getty Images

ソフィアの街並みとアレクサンドル・ネフスキー大聖堂 ©︎brunocoelhopt, iStock / Getty Images Plus, Getty Images
・第2部 17:45-19:30 ネットワーキング(有料)
・言 語: 英語(必要に応じ、日本語・ドイツ語の補足あり)
・対 象: 日独の学術・文化交流やSDGsに関心のある方
・場 所: ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川ホール(第1部)、Café Müller (ネットワーキング)
・プログラム: 詳細は、ゲーテ・インスティトゥートヴィラ鴨川のウェブサイトに掲載
・申し込み: 終了しました
当日の様子・報告
Kamogawa Talkは初の試みでしたが、学内外から幅広く、約40名が参加しました。
京都大学の研究者・職員・学生に加え、京都橘大学、京都産業大学、同志社大学、立命館大学などの近隣の大学の方々、山岡記念財団、Springer Nature、国際交流基金等の財団・文化機関の方々が集い、中には外国人留学生やドイツから一時帰国中の方も参加し、垣根を超えた意見交換が行われました。
日独を行き来する東南アジアと東欧の専門家をパネリストに招き、「移民」をテーマに議論した第1回 Kamogawa Talkですが、その議論は両地域の比較・報告にとどまらず、外国人観光客・留学生をはじめ多様なバックグラウンドをもつ人々が集うこの古都・京都においても、どのように次世代の文化を醸造・発信し若者の活躍を応援してゆくか、という問題意識を参加者それぞれが身近に思い描く機会となりました。第一部の後の交流会では、ドイツビールやグリューワイン、プレッツェルを片手に様々な言語が飛び交い、夫婦・親子連れでも楽しめるネットワーキングの場となりました。
今後も若手研究者の国際的な活躍を後押し、国境やアカデミアの枠を超えて広く社会の問題意識を共有できる、活動・ネットワークの場を提供してゆきます。
また次回も、多くの方々の参加をお待ちしています。

Enzio Wetzel 館長からの開会挨拶

Damaledo研究員による、東ティモールにおける移民に関する紹介

パネルディスカッションの様子(左からDr. Petrov, Dr. Damaledo, Dr. Wittfeld)

質疑応答・ディスカッションの様子
【お問合せ先】
学術研究支援室【間:AI DA】担当(園部、桑田、仲野、鈴木、Wittfeld、中久保)
Tel: 16-5179(内線)| E-mail: aida(at)kura.kyoto-u.ac.jp
![若手研究者の国際的な活躍をサポートする[間:AI DA]プログラム](/exchange/aida/wp-content/themes/kyoto-u-daad/img/logo-aida.png)